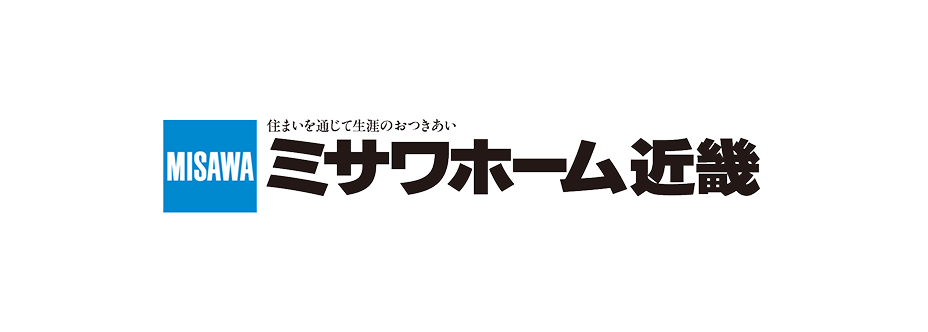住まいのお役立ち情報
資金計画について
家を買うタイミングを考えてマイホームを手に入れよう!

これからご紹介する6つのポイントを参考に、無理なく、そして無駄のない資金計画を考えましょう!
家を買うタイミングを考える6つのポイント
1.人生を俯瞰する
将来のライフイベントやライフプラン全体を見渡し、長期的な視点で住まいの計画を立てましょう。
2.金利の動向
市場の金利動向を注視し、低金利のタイミングを活用して総支払額を抑える工夫をしましょう。
3.教育プラン
お子さんの成長に伴う教育費を見据え、必要なタイミングで資金を準備できるように計画を立てましょう。
4.家族構成
家族の人数やライフスタイルの変化を考慮し、将来も快適に暮らせる住まいを選びましょう。
5.セカンドライフの計画
定年後の生活や趣味、ライフスタイルを見据えて、長く安心して暮らせる住まいを考えましょう。
6.年収の動向
世帯主だけではなく、ご家族の将来的な収入の変化やキャリアプランを考慮し、無理のない返済計画を立てることが重要です。
ライフデザイン(人生設計)とマイホームデザイン
ライフデザインに合わせたマイホーム計画を考える際には、まず家の目的を明確にすることが大切です。
家族構成やライフステージに応じて、住まいに求める役割は変わっていきます。
例えば、子育て中は家族みんなが快適に過ごせる家を重視し、ご両親との同居が必要かどうか、子どもが独立した後の夫婦二人のシニアライフを見据えた住まいにするか、といった具合です。
また、将来の変化に備えて、最初からバリアフリー設計を取り入れたり、柔軟に間取りを変えられるようにしておくこともポイントです。
こうして、家族全員の成長やライフスタイルの変化に合わせた住まいをデザインしていきましょう。
住宅ローンについての疑問に答えます
住まいに関する疑問を解消しましょう!
住宅ローンは、どのようなものがありますか?
- 民間融資
-
銀行ローン
多くの銀行が提供しており、金利タイプ(変動金利、固定金利、固定期間選択型)や返済期間、融資額などが多様なローン商品があります。
信用金庫ローン
地域の信用金庫が提供するローンで、地域密着型のサービスが強みです。
信託銀行ローン
資産運用なども手掛ける信託銀行が提供するローンは、金利や返済プランが多様化している場合があります。 - 公的融資
-
財形住宅融資
財形貯蓄を利用する公的ローンで、一定額以上の残高があれば利用できます。
自治体融資
都道府県や市町村が提供するローンで、地域密着型のサービスが強みです。 - 協調融資
-
フラット35
全期間固定金利の住宅ローンで、返済期間が最長35年までというメリットがあります。
住宅金融支援機構融資
住宅金融支援機構が提供する公的ローンで、固定金利で長期返済ができるのが特徴です。
この十数年は超低金利のトレンドで民間融資が主流になってきました。金利上昇が予想される局面においては安心できる固定金利の「フラット35」の価値も見直されてきています。勤務先の融資制度を活用するときは、在職期間などご自身のキャリアプランを考慮しましょう。また、ハウスメーカーなど特定の金融機関との提携ローンがある場合は、一般の融資より有利なこともあるので比較検討し、少しでも総返済額が少なくなるように、有利な選択をしましょう。
住宅ローンの基本はムリ・ムダが少ないこと。ローンは80歳まで組めることが多いですが、長期のプランをお考えの場合には、ご退職後、年金中心の生活になってからのことも十分考慮して無理のない計画を進めてください。
住宅ローン選びのポイントを教えてください。
住宅ローンの基本は次の3点です。
・金利(少しでも低い金利)
・借入期間(少しでも短い期間)
・借入額(少しでも少ない金額)
これら3つの条件にプラスしてご自身のライフプランを考慮することも忘れてはなりません。
例えば、返済期間について、当初は毎月の返済額に無理はないが、数年後お子さんが大学に入った時にかなり厳しくなりそうな場合は、無理して返済期間を短くするのではなくて、少し長めにして毎月の返済額を抑えるほうがベターかもしれません。借入額については、自己資金の箇所で説明していますのでご参照ください。
大切なのは当初立てた返済計画で長期的に無理なく払い続けることができるか?
<無理のない返済計画>これが最も大切なポイントです。
良い住宅ローンってどんなローンですか?
誰しも本当は現金で買いたいところですが、現実はローンを使わざるを得ないものです。
『良い住宅ローン』を選ぶという観点ではなく、『少しでも悪くないローン』を選ぶと考えるほうが良いかもしれません。マイホーム購入時は<住宅ローン選び>に注力を傾けられますが、ローンはマイホームを購入する為の<手段>であって、<目的>はマイホームの購入です。
キャンペーンや優遇金利ばかりに気を惹かれることなく、他にかかる費用(融資手数料・保証料・団体信用保険料・繰上返済手数料)なども十分に考慮してください。
また、優遇金利を受ける場合は、その適用期間は全期間なのか当初だけなのかも必ず確認しておきましょう。
自己資金(頭金)は何割必要ですか?
購入資金を100%ローンでまかなうことも可能な場合もありますが、自己資金は多ければ多いに越したことはありません。
頭金が多いほどローンを組む額も減りますので毎月の返済額も少なくてすみます。計画時に家族会議・親族会議などを開かれることをおすすめします。ご両親など資産状況に余裕をお持ちの場合は、税制などを考慮し、資金援助を受けられるのも一手だと思います。その上で購入後の生活のことを考え、最初に投入する金額を決めましょう。
例えばマイカーの購入予定が数年後に迫っているときは、その分を予算取りして残しておいたほうが無難です。
結局、数年後に住宅ローンより高い金利のマイカーローンを借りることになるのは避けましょう。
収入に対する返済額(返済比率)は何%くらいが適当でしょうか?
住宅関連雑誌などでは、<返済比率は25〜30%以内に抑えましょう>と載っていますが、一概には言えません。
例えば年収400万円の方と800万円の方では同じ返済比率25%といっても年間返済額は前者100万円、後者200万円となりまったく異なります。精一杯切り詰めた生活をした場合は家族構成が同じであれば基本的にかかる生活費は年収には比例しない事が多いです。どちらも基本的生活費が毎月10万円(年間120万円)と仮定すると、前者は住宅ローンと生活費を合わせて220万円を使うことになります。後者は320万円です。
それ以外に使える費用は年収400万円の場合は180万円、年収800万円の場合は480万円となり、明らかに年収が多いほうが余裕資金が多くなります。したがって年収が高いほど返済比率は高くても大丈夫、低いほど返済比率は低めに抑える必要があると言うことになります。
嗜好品や外食、旅行の頻度などライフスタイルが違えば、基本的にかかる生活費は各ご家庭で異なります。書物や雑誌やネットから得た情報だけに振り回されず、ご自身の家庭にあてはめて慎重に考えましょう。
金利タイプの特徴(メリットとデメリット)を教えてください。
①固定金利型
②変動金利型
③固定金利期間選択型
の3つの基本形があります。
どれか1つを選ぶのではなく、固定金利と変動金利を組み合わせたりできる金融機関もあり、選択肢も増えています。
主なメリットとデメリットをご紹介します。
横にスクロールできます
| 金利のタイプ | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 固定金利型 |
|
|
| 変動金利型 |
|
|
| 固定金利期間選択型 |
|
|
固定と変動どちらが良いですか?
どちらが良いか一概には言えません。経済の動向は不透明感を増しています。金利の条件は借入金額や借入期間などの条件によって変わります。選択される際には、家族構成やお子様の教育費など今後のライフプランも考慮すると良いと思います。
例えば、50歳前後で少し資金的に余裕があって、10年後に退職金で一括返済を考えておられる方は、変動型もしくは短期固定金利型を選ぶほうがベターかもしれません。長期固定金利を選ぶと当初から高めの金利になり、短期間固定の金利と比べると要らない利息を支払うことになるかもしれません。30歳前後で今後お子様の教育費の負担が心配な方でサラリーの上昇なども予想しにくい方は、毎月のお支払額がずっと見通せる長期固定型を選ぶほうがよさそうです。
このようにご家庭の事情によって異なりますので、一般論に流されず、ケース・バイ・ケースで考えることをおすすめします。
借入額・・・銀行からOKが出たが、返せるかどうか心配。
借入可能額(金融機関が貸してくれる額)と返済可能額(実際に返せる額)は異なります。金利が低いほど返済期間が長いほどたくさん借入できますが、ローン返済終了まで無理なく返済できるかどうかのほうが大切です。現在賃貸で生活されている方は今の年間の家賃総額(管理費や駐車場代など)と購入後の住宅ローンの年間差額がどの程度になるか?住宅ローン以外にかかる費用(固定資産税など)も含めて比較してみましょう。
例えば、購入前の年間家賃総額より購入後の年間総額のほうが50万円高い場合は、現在年間50万円以上貯蓄できていないと、購入後かなりの節約を強いられることになります。ローンや固定資産税などを払っても目標の貯蓄ができるくらいが好ましい計画と言えます。
収入合算のメリット・デメリット
収入合算する最大のメリットは借入金額を多くすることができることです。また、連帯債務の場合は夫婦それぞれ住宅ローン控除を受けることができます。デメリットは借入金額が多くなるので、毎月の返済負担が大きくなる点です。
例えば、借入をした後に育児などで妻が仕事を辞めたり働いてもパートでそんなに収入がなかった場合、合計収入が減るので返済負担が大きくなります。このようなことが予想される場合は安易に収入を合算せずに、計画の段階で、将来妻が仕事を辞めた場合を想定した上で資金計画を練ることをおすすめします。
※後述の「連帯保証と連帯債務はどうちがうの?」と関連していますのでご参照ください。
連帯保証と連帯債務はどうちがうの?
共働き夫婦二人とも住宅ローン控除を受けたい時など連帯保証と連帯債務との違いが分からずに失敗するケースがありますので注意が必要です。
例えば夫婦で共同して住宅ローンを借りるとき、連帯保証の関係では主債務者である夫 (または妻)は住宅ローン控除の適用を受けられますが、連帯保証人となる妻(または夫)は住宅ローン控除の適用を受けられません。これに対して夫と妻とが連帯債務者の場合(共有の登記が必要)には、お互いに住宅ローン控除の適用を受けることができます。
例えば3,000万円の住宅ローンを夫名義で借りて、妻が連帯保証人となったとき、主たる債務者はあくまでも夫であり、妻は保証人に過ぎません。ところが、支払いの延滞等が生じて債権者から保証人へ請求されたとき、通常の保証人であれば「まずは債務者である夫に請求して欲しい」と主張する権利があるのに対し、連帯保証人にはその権利がなく、請求を受ければ直ちに弁済の責任を負うことになります。
一方、連帯債務の場合には例えば3,000万円の住宅ローンに対して夫も妻も共に債務者となります。債権者は夫に対しても妻に対しても同等に請求できるわけです。この場合、夫と妻の債務は3,000万円ずつになります。半分ずつ1,500万円の債務になるわけではありませんが、住宅ローン控除の計算においてはそれぞれの登記された持分によって控除を受けることができます。
民間金融機関では配偶者の収入は合算できても、その配偶者は連帯債務者でなく連帯保証人にしかなれないケースもあり、このような場合はそれぞれが住宅ローン控除を受けることができません。よって、連帯債務に対応していない金融機関の場合、夫婦で住宅ローンを借りるときは夫と妻のそれぞれが各自で住宅ローンを組む必要があります。夫婦連帯債務に対応している住宅ローンかどうかを必ず事前に確認する必要があります。
※前述の「収入合算のメリット・デメリット」もご参照ください。
ローン以外にかかる費用にはどんなものがありますか?
一般的に<諸費用>と言われている、ローン以外にかかる費用があります。入居後にかかる費用もありますのでしっかりと計画に入れておきましょう。 通常は新築住宅の場合で住宅価格の3%〜5%、中古住宅の場合で5%〜10%程度といわれていますが、購入物件によって事情が異なります。あとでトラブルにならないように、実際の金額はご契約前にしっかりと確認しておきましょう!
- 購入時にかかる費用
-
- 契約費用・ローン手数料・保証料・印紙税・登記費用・登録免許税・司法書士の費用
- 火災保険料・地震保険料(任意加入ですが、金融機関によっては質権の設定が必要な場合もあります。)
- 修繕積立基金・管理準備基金(マンションの場合)
- 入居後にかかる費用
-
- 不動産取得税(1年目のみ必要)
- 固定資産税・都市計画税(毎年必要)
- 管理費・修繕積立金(マンションの場合毎月必要)
その他注意すべき大切なこと
住宅購入時には、住宅ローン控除と贈与税の優遇策を上手に活用することが大切です。 住宅ローン控除は、一定の条件を満たせば所得税が軽減される制度で、毎年の年末残高に応じて控除額が決まります。また、親や祖父母からの資金贈与を受ける場合には、一定額まで非課税となる特例制度があり、これらを上手く利用することで、購入時の負担を軽減できるので、常に最新情報をチェックすることをおすすめします。